現役社労士のあずきごはんです。
私は、2回目の受験で社労士試験に合格しました。現在は社労士業務を行いながら、このブログを通じて試験勉強のコツやキャリアアップに関する情報を発信しています。
今回の記事では、私の体験を通して「フルタイム勤務や育児をしながら社労士試験に合格するための勉強法とスケジュール」についてご紹介します!
 あずきごはん
あずきごはんこんな方におススメの記事です!
・仕事や育児と両立しながら合格を目指している方
・独学か資格学校を利用するか迷っている方
・勉強時間の確保に悩んでいる方
社会保険労務士の勉強方法
1回目の勉強方法:映像講義コース(通学、資格の大原)
選んだ理由
私は当時、フルタイム勤務をしながらの受験で、帰宅後に自宅で集中できる自信がありませんでした。仕事終わりの疲れた状態ではなかなか勉強が進まず、モチベーションも下がりがち…。
そのため、週2回の講義に通うことで、学習ペースを維持しやすい通学による映像講義コースを選びました。
実際に受講してみて感じたこと
映像講義コースは、個別のブースで録画された講義を聴くスタイルです。
指定の時間にブースを予約して通学する為、自宅よりも集中して勉強することができます。
社労士受講生と直接やり取りすることはないのですが、税理士、公務員などの難関資格に向けて勉強する方が沢山いたので、「みんなも頑張っているんだ」と感じ、モチベーションの維持につながりました。
ただ、私は仕事の都合でどうしても一定のペースで講義受講することが難しく、一度期間が開いてしまうと、その分の補講を受けるのが面倒に感じることも…。
また、資格学校の授業料は決して安くないので、「本当にこの方法がベストなのか?」と悩むこともありました。
メリット
✅ 全国レベルの講師の授業が受けられる
✅ 資格学校の自習室が使える(集中しやすい環境)
✅ 受講生同士の交流ができ、モチベーションが維持しやすい
デメリット
❌ 予約制なので後回しにしがち
❌ 毎回の移動が負担になる(特に仕事終わりや休日)
❌ 受講料が高め
2回目:WEB通信コース(ⅰ.D.E社労士塾)
選んだ理由
自宅で映像講義を受けるスタイルです。
1回目の受験で基礎知識と勉強習慣は身についたので、2回目はより効率的な学習方法を選びました。通学時間を削減し、スキマ時間を有効活用するために、WEB通信コースを選びました。
※ⅰ.D.E社労士塾は、残念ながら閉塾されました。
実際に受講してみて感じたこと
朝は早めに起きて出勤前に1時間、夜も仕事から帰宅後に1時間、週末はカフェや図書館で7~8時間ほど勉強するというスケジュールを組みました。
1回目で勉強習慣がついていたので、特に苦ではありませんでした。
ただ、完全自己管理が必要なので、計画を立てるのが苦手な人は途中で挫折する可能性があるかもしれません。
私は「この日は厚生年金法の過去問を5ページ終わらせる」と具体的な目標を立てて、進捗を見える化することで乗り切りました。
メリット
✅ 好きな時間に受講できる(朝活・夜活に最適)
✅ 全国の受験生向けのハイレベルな講義
✅ 何度でも繰り返し視聴可能(理解が深まる)
デメリット
❌ 完全自己管理が必要(計画的に進めないと挫折しやすい)
❌ 仲間が見えないので孤独を感じる
独学 vs 資格学校 どちらが良い?
- 社労士試験は 法改正・例外条文も多く、独学では理解が難しい
- 2回目以降の受験者は独学でもOK
効率的な勉強スケジュール
資格の学校を活用することで、初学の勉強時間は年650時間程度で合格ラインに達することができました。
2回目の勉強時間も同程度だと思われます。
1年目の年間勉強スケジュール
| 期間 | 月の勉強時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 1~2月 | 50時間×2ヶ月 | 基礎固め(講義+テキスト読み込み) |
| 3~5月 | 70時間×3ヶ月 | 過去問演習+知識補強 |
| 6月 | 90時間 | 模試・苦手科目対策 |
| 7~8月 | 120時間×2ヶ月 | 直前対策(総復習+模試) |
合計:約650時間
合格に近づく勉強法
効率良い勉強も合わせて、繰り返しの勉強が効果的です!
① 過去問を繰り返す
- 過去10年分の問題集を 「〇△×」で管理
- 〇(正解)が100%になるまで解く!
② 単語カードを活用
- ダイソーのカードリングで 自作単語カード を作成
- スキマ時間(通勤・昼休み・寝る前)に確認
まとめ
✅ 初学者は資格学校がオススメ(理解が深まる&自己管理が不要)
✅ 資格の学校活用では勉強650時間程度でも
✅ 過去問を徹底的に繰り返す&単語カードを活用
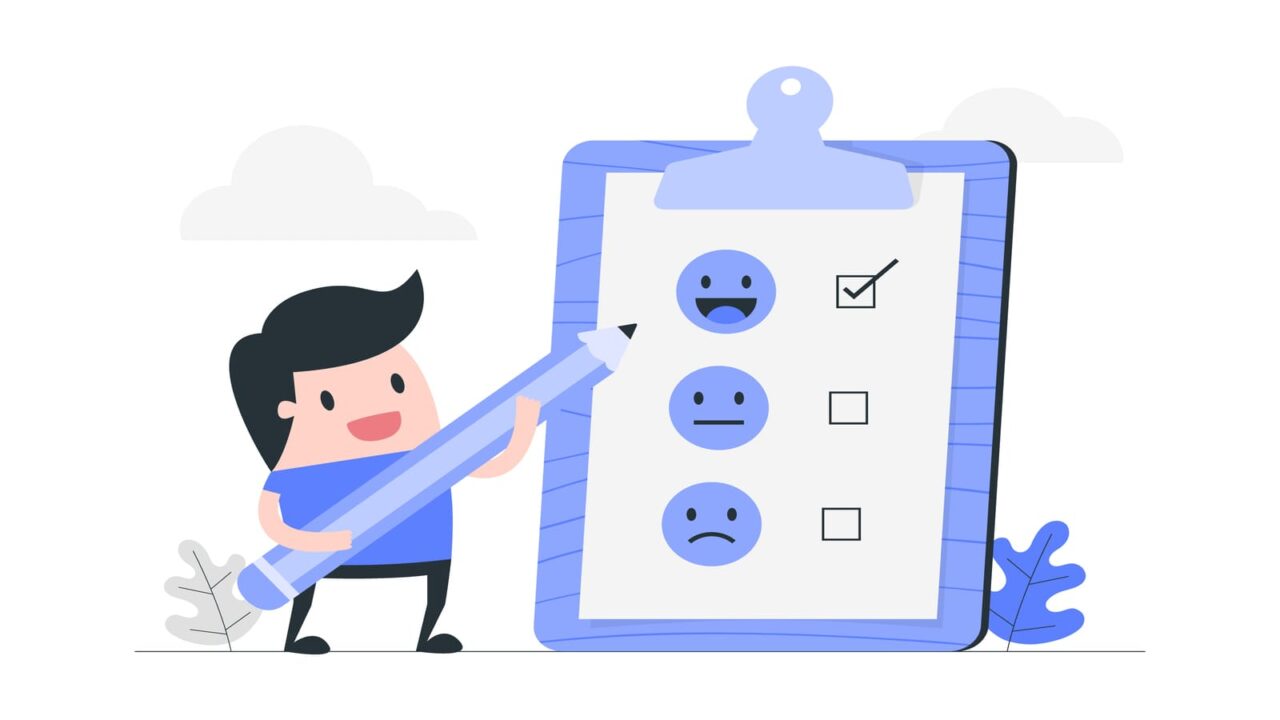
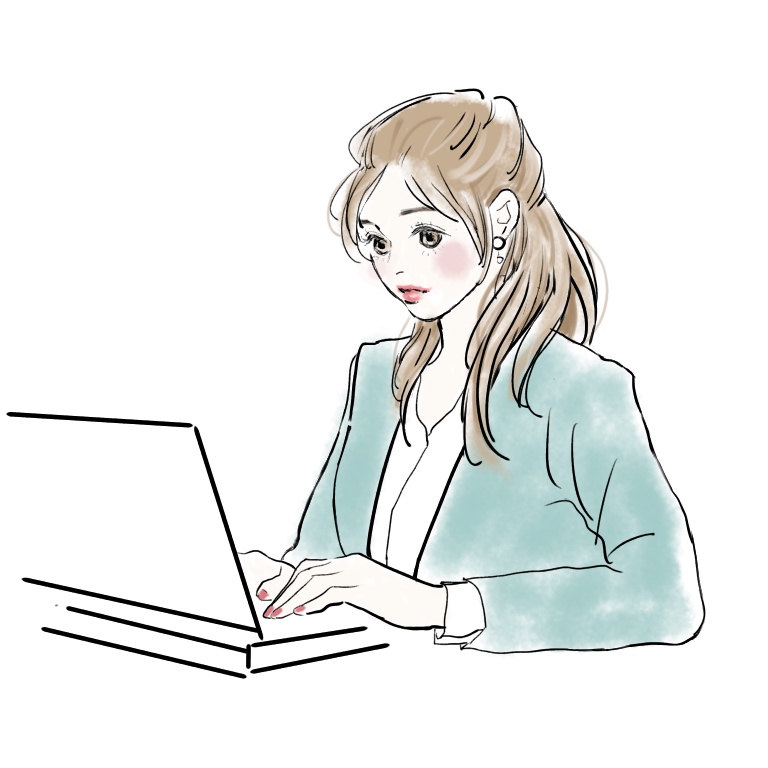

コメント